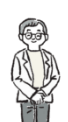私は司法書士として、これまで多くの相続案件を担当してきましたが、今回のケースは兄妹間の意見の違いが大きく、調整に慎重な対応が求められる案件でした。
背景事情
相談者のMさん(66歳)は、東京都練馬区在住の長男であり、長年両親と同居し生活を支えてきました。両親が立て続けに亡くなったことで、相続手続に関するご相談を受けました。
母の遺産は預金1500万円程度であったため、Mさん自身で対応可能と考えていました。しかし、父の遺産には自宅や貸駐車場を含む路線価で5000万円相当の不動産と2500万円程度の預貯金があったため、他の相続人との協議が必要でした。 Mさんは、妹のAさん(新潟県在住)と弟のBさん(都内在住)に対し、「自分がすべての財産を相続する代わりに、それぞれ500万円ずつ支払う」という提案をしましたが、二人は納得せず、話し合いが進まない状況でした。
私が受任することとなり、まずMさんから詳しい話を聞くと、兄妹間で意見が大きく異なり、特にAさんは「兄が長男だからといって全てを相続するのは不公平」と強く主張していました。また、葬儀費用の負担についても意見が分かれており、話し合いが膠着状態に陥っていました。
解決のポイント・当事務所の対応
このままでは家庭裁判所での遺産分割調停に進む可能性もあるため、私はAさんとBさんの意向を直接伺うため、面談することにしました。
〇Aさんとの面談(新潟県まで訪問)
・「兄が不動産を相続すること自体には反対しないが、その分公平に、預貯金は私と弟で分けるべき」
・「葬儀費用は喪主である兄が負担するべき」
・「母の相続も単独で考えるのではなく同様に預金は私と弟の二人で分けるべき」
・「話し合いで解決したいが、家庭裁判所での調停も視野に入れる」
〇Bさんとの面談(都内にて)
・「基本的に姉の考えに同意」
・「葬儀費用については、三等分するのが妥当ではないか」
・「調停は避けたい。できるだけ話し合いで解決したい」
私はMさんに、AさんとBさんの考えを伝え、以下の点を再考するよう助言しました。
①遺産分割の公平性
不動産はMさんが相続するが、お母様分含めて預貯金はAさんとBさんで均等に分ける。
②葬儀費用の分担
Mさんが3分の2、Bさんが3分の1を負担する。
③調停回避のメリット
家庭裁判所での遺産分割調停に進めば、最終的にMさんにとってより不利な分割になる可能性がある。
※参考記事「葬儀費用の扱いについて、法的・税務的観点から分かり易く解説」
結果・お客様の声
Ⅿさんは熟考の末、妹と弟の意見を受け入れることを決断し、ギリギリのところで話し合いによって遺産分割協議が成立しました。
〇Mさんが自宅および貸駐車場を相続
〇お父様の預貯金2500万円、お母様の預貯金1500万円をAさんとBさんで均等に分割
〇お母様分含めて葬儀費用はMさんが3分の2、Bさんが3分の1を負担
〇お母様の遺産分割協議書も司法書士に依頼する。
Mさんからは、以下のメッセージをいただきました。
「正直、自分一人で解決できると思っていました。でも、いざ話し合いを始めると、兄妹間の意見の違いが大きく、自分ではどうしようもなくなってしまいました。 司法書士の先生が間に入ってくれたおかげで、お互いの意見を整理することができ、冷静に話し合うことができました。兄妹間の関係は、やはりぎくしゃくしたままですが、少なくとも絶縁することにはなりませんでした。何より、家庭裁判所の調停に進むことなく話し合いで解決できたことは、大きな安心につながりました。ありがとうございました。」
本件は、兄妹間の意見の違いが大きく、話し合いの継続が難しい状況でしたが、早期に第三者である専門家が介入することで、調停を回避し、協議による解決が可能となりました。また、兄妹間の関係性を考慮し、感情的な対立を最小限に抑えるよう努めた結果、完全に納得したとはいえないまでも、互いに一定の理解を示す形で解決に至ることができました。

相続でお困りの際は、ぜひご相談ください。