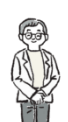背景事情
ご相談に来られたのは、東京都三鷹市にお住まいの72歳の女性、Oさんでした。お父様(享年97歳)が亡くなられたあと、相続手続きに関するご相談でお越しいただきました。
お父様は、公正証書による遺言を残されていました。その内容は、自宅不動産は長女であるOさんへ、預貯金については長男に2割、二男に2割、長女のOさんに4割、二女に2割を相続させる、というものでした。
ところが、問題が発生しました。というのも、長男が、お父様より5か月早く亡くなられていたのです。遺言には、このような「受遺者が先に亡くなった場合」の予備的な記載がなく、長男に遺贈される予定だった財産については、法定相続人全員での遺産分割協議が必要となりました。
しかも、遺言執行者として指定されていたのはOさんご自身。ご高齢のOさんが、複雑な状況のなかで手続きを進めなければならない状況でした。
疎遠な代襲相続人との連絡が最大の壁
ご相談をお受けしてまず感じたのは、Oさんの誠実さと責任感です。お父様と同居され、通帳の管理や生活費の支出、葬儀費用の立て替えなど、身の回りのサポートを最後までなさっていました。
ただ、問題は残された家族関係の構図にありました。Oさん・長男・二女の3人は連絡を取り合える関係でしたが、養子の長男の代襲相続人であるお孫さん2名とは疎遠で、連絡先もはっきりせず、Oさんが直接進めるのは難しい状況でした。
「自分では無理だから、代わりに動いてもらえないか」
そうOさんに頼まれ、私たちが正式に受任することになりました。
当事務所の対応
財産の全体像を把握し、代襲相続人に丁寧な説明を
まず取り掛かったのは、相続財産の調査でした。特にOさんが日々の生活費や医療費として引き出されていた預金については、用途と金額を丁寧にヒアリングし、相続財産に含めるべき範囲を明確にしました。
次に、代襲相続人のお二人と連絡を取り、状況をご説明しました。
- 長男に遺贈される予定だった財産については、遺言が効力を持たないこと
- したがって、その財産は法定相続人全員の協議が必要であること
- Oさんが生前に相続財産から引き出し支出した生活費や葬儀費用の説明
- 他の相続人3名は、お二人がそのまま相続する内容で合意していること
これらを丁寧に説明し、財産の全体像と分配方法を納得いただいたうえで、最終的に全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成することができました。
相続財産の分配手続き
協議の末、遺言で定められた方針を尊重する形で、長男分は代襲相続人が取得し、不動産や預貯金の分配もスムースに進みました。
不動産の名義変更や金融機関の解約手続きについては、遺言の代わりに遺産分割協議書を使用しました。協議書の中には公正証書遺言の存在を明記し、全員がその内容を尊重していることも記載しました。
結果として、形式上は遺言とは異なる処理となりましたが、実質的にはお父様の意思に沿った、平穏な解決となりました。 さらに印象的だったのは、一周忌にOさんが甥にあたる代襲相続人のお二人を招いたところ、これまで疎遠だった関係に少し温かさが戻るきっかけとなったことです。
解決のポイント
本ケースでは、解決のポイントが複数ありました。
- 遺言にない「受遺者の死亡後」の処理は、遺産分割協議で対応
- 生前の引出しは目的と金額を精査し、相続財産としての整理が必要
- 疎遠な相続人とも丁寧な説明と連絡を心がけることが信頼の鍵
- 遺言があっても、実務では遺産分割協議書を使う場面がある
※参考記事①「遺言の「予備的条項」とは何か?」
※参考記事②「遺言があっても遺産分割協議は可能?」
お客様の声
「自分で遺言の内容をもとに手続きを進めるつもりでしたが、思いもよらない落とし穴がありました。疎遠になっていた甥たちとのやりとりも、最初はどうしていいかわからず…。
でも、先生に丁寧に動いていただいたおかげで、無事に相続をまとめることができました。
自分たちではとてもできなかったので、本当に感謝しています。」
遺言作成の依頼を受けたとき、予備的条項をどこまで記載するか、いつも悩みます。受遺者が個人だといつかは亡くなるので切りがないのと、遺言者の意思として決められないことがあるためです。本ケースのように、受遺者死亡後の予備的条項がないとその部分は無効となり、その部分は法定相続人全員で協議を行う必要が生じます。第三順位の相続で相続人の数が多い場合などは手続きが大変になり、予備的条項がないと当該相続財産が宙に浮いてしまうことにもなりかねません。遺言作成の際はご留意ください。

相続でお困りの際は、ぜひご相談ください。