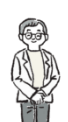背景事情
夫が亡くなったのは、ある冬の日のことでした。
ご相談くださったTさん(78歳・東京都武蔵野市)は、長年連れ添ったご主人を亡くし、悲しみの中で相続手続きを進めなければならない状況でした。
ご主人には離婚歴があり、前妻との間にお子さんが一人いることは分かっていました。しかし、その方とは一度も会ったことがなく、居所も不明。加えて、Tさんとご主人の間には長男と長女がおり、相続人は全部で4名。法定相続分はTさんが2分の1、お子さん3名がそれぞれ6分の1という形です。さらに、長男は生前にご主人から生活費援助として約600万円を受け取っており、Tさんは葬儀費用として約200万円を負担していました。相続財産は自宅(固定資産評価額約2000万円)、預貯金約2500万円、そしてTさんが受取人の死亡保険金1500万円という内容でした。
当事務所の対応
代理人弁護士が登場
まず着手したのは、前妻との子の居所調査です。戸籍の附票から住所を突き止め、手紙を送ったところ、間もなく代理人弁護士から就任通知が届きました。
その通知には、「私はTさん、長男、長女の代理人ではないため、今後は3名に直接連絡する」と記されており、この時点で私は相続人間の直接協議を促し、私は財産調査と財産目録の作成に専念する方針としました。
直接協議での合意形成
長男・長女は、代理人弁護士と直接やり取りを開始。協議の結果、前妻との子が法定相続分に相当する代償金を受け取ることで合意が成立しました。
自宅の評価が唯一の争点となりましたが、先方代理人の主張には客観性があり、金額も不当に高額ではなかったため、弁護士をつけずとも納得感のある解決に至れると判断しました。
また、葬儀費用については相続人全員の同意がない限り相続財産からの支出は難しく、弁護士の有無にかかわらず結果は変わらないため、この点も含めて総合的に判断したうえで、Tさんら3名は弁護士を立てずに進めることを決断しました。
解決のポイント
本ケースでは、解決のポイントが複数ありました。
- 相続人に前妻との間の子がいる場合は、まず居所調査から着手
- 代理人弁護士が関与しても、争点が限られれば弁護士を立てずに解決可能な場合もある
- 自宅評価が唯一の論点で、先方主張が合理的だったため早期合意が可能
- 葬儀費用の扱いは相続人全員の同意が必須で、弁護士の有無で結果は変わらない
- 生前贈与を含めて財産目録を正確に作成し、登記・預金解約まで一括対応
お客様の声
正直、自分たちだけではどう進めてよいか分からず、不安でいっぱいでした。
相続人の一人に弁護士がついたと聞いたときは、「裁判になるのでは」と心配しましたが、先生がアドバイスをくださり、やるべきことを整理してくれたおかげで、安心して進められました。自宅の評価や葬儀費用の扱いについても、事前に弁護士を立てた場合と結果は変わらないことを説明してもらえたので、納得して判断できました。結果として、全員が納得する形で遺産分割ができ、自宅や預金の名義変更も無事に終わりました。
自分では解決できなかったことを最後までサポートしていただき、本当にありがとうございました。
本ケースでは、遺産分割協議成立後に私が協議書を作成し、相続登記や預貯金解約など、残る実務手続きを一括して行いました。相続人の一人に弁護士が付いた場合、司法書士は弁護士法の制約で関われる範囲が限られますが、今回は相続人本人を通して必要なやり取りを続け、最後まで案件を完了させることができました。

※参考記事 相続人の一部に代理人弁護士がついた場合の相続手続き|前妻・前夫の子どもが関与するケースの注意点
相続でお困りの際は、ぜひご相談ください。