
司法書士
藤川健司
司法書士事務所 リーガル・アソシエイツの代表司法書士。三鷹市、武蔵野市、調布市、杉並区、中野区を中心に相続専門の司法書士事務所として、相続全般のサービスを提供。業務歴30年以上。弁護士事務所での実務経験、起業経験を活かして、これまでに2000件以上の相続案件を手掛ける。
CONTENTS
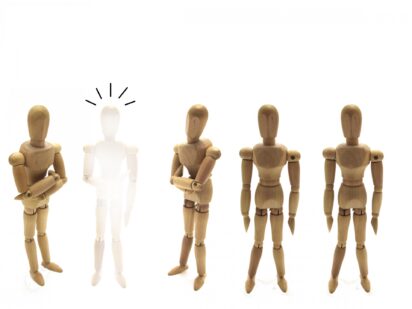
相続手続きにおいて、相続人の一人が居所不明や連絡不能な場合、遺産分割協議が進められず深刻な問題となります。本記事では、不在者財産管理人の選任手続きや、連絡不能な相続人がいる場合でも可能となる預金解約の実務対応について詳しく解説します。不動産があるケースの注意点や、専門家を活用するメリットについても紹介し、複雑な相続問題に対する実践的な対応策をわかりやすくご案内します。
目次
相続手続きを行う際には、原則として全ての相続人が関与する必要があります。これは、遺産分割協議を行う場合でも、相続財産を管理・処分する際でも共通のルールです。しかし、相続人の中に居所が不明だったり、居所は分かっていても連絡がつかない人がいる場合、手続きがストップしてしまうことがあります。
特に遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要となるため、一人でも連絡が取れなければ協議が成立しません。このような状況は、他の相続人にとっても大きなストレスとなり、手続きを進める上での大きな障害となります。 このセクションでは、こうした問題がなぜ起こるのか、そして相続人全員の関与がなぜ求められるのかという基本的な背景について解説しました。次のセクションでは、居所が不明な場合に取りうる具体的な法的手段について見ていきます。
相続人の居所が不明で、連絡も取れない場合には、裁判所に対して「不在者財産管理人選任申立て」を行うことができます。この制度は、行方が分からない相続人に代わって財産管理を行う人を選任することで、相続手続きを進められるようにするための法的手段です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所によって選ばれ、原則として弁護士などの専門家が就任することが多いです。この管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議などに参加し、他の相続人と協議をまとめていくことが可能になります。 この手続きは、行方不明であることを証明するために一定の調査が必要であり、家庭裁判所への申し立てやその後の管理人の活動にも時間がかかることがあります。しかし、居所不明の相続人がいる状態で手続きを進めるには、現実的かつ有効な手段といえるでしょう。
居所が分かっているにもかかわらず、相続人と連絡が取れないというケースも珍しくありません。この場合、不在者としての扱いができないため、不在者財産管理人の選任手続きは利用できず、相続手続きはより難航する傾向にあります。
なぜなら、法律上はその相続人が「不在」ではなく、「協議に応じない状態」にあるだけと判断されるからです。そのため、遺産分割協議は進められず、他の相続人が勝手に財産を分け合うことはできません。連絡がつかない理由が一時的なものである可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
こうした場合には、内容証明郵便などで正式な連絡を試みた記録を残し、将来的に家庭裁判所に対して調停や審判を申し立てる際の証拠とすることが重要です。ただし、連絡が取れない相続人は、調停の場にも出頭しない可能性が高く、その場合、最終的には裁判所による審判に移行します。審判では、原則として法定相続分に基づいた分割が行われるため、時間と費用をかけたにもかかわらず、結果としては最初から予測できた内容になることも少なくありません。 こうした背景を踏まえると、単独で進められる手続きがないかを探ることや、場合によっては専門家の力を借りて解決への道を模索することが現実的です。
相続人の一部と連絡が取れない場合でも、相続財産のうち預金については、一定の条件を満たすことで解約手続きが可能となる場合があります。特に金融機関によっては、他の相続人が責任をもつ旨を記載した念書を提出することで、相続人全員の実印や印鑑証明書が揃っていなくても解約に応じてくれるケースが存在します。
金融機関は、二重払いのリスクを負わないようにするため、預金者に対しては債務者という立場ではありますが、このような解約手続きにおいてはどこも慎重な態度をとります。しかし、内部事情としては、未処理の相続案件をいつまでも抱え続けることを避けたいという本音もあります。そのため、二重払いのリスクがないと判断できれば、できる限り速やかに解約処理を終えたいというのが金融機関側の実情でもあります。
こうした背景もあり、残りの相続人が誠実に調査を行い、連絡を試みた経緯を念書としてまとめ、それを提出することで、金融機関としても納得のいく対応が取られたと判断すれば、例外的に解約を認めることがあります。念書の内容としては、連絡を試みたが不調であったことや、今後その相続人から請求があった場合には他の相続人が責任を持つことなどを明記する必要があります。 また、調査の証拠や内容証明郵便の控えなどを添付すれば、さらに信頼性が増し、手続きがスムースになる可能性があります。
こうした対応は、あくまでも実務上の柔軟な措置ではありますが、実際に成功する事例も多いため、まずは試してみることが現実的な解決策となるでしょう。
一方で不動産の名義変更(登記)は、金融機関のように裁量で対応できる余地はなく、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書が必要で法的な手続きが必須となります。
相続手続きは、関係者全員の合意や法的な手続きが必要となるため、非常に複雑になりがちです。特に、相続人の中に居所不明や連絡が取れない人がいる場合、問題はさらに深刻化し、個人の力では対応しきれない場面が多くなります。こうした状況においては、弁護士や司法書士など、相続に詳しい専門家の力を借りることが重要です。
専門家は、相続人調査の方法や不在者財産管理人の申立手続き、念書の作成や金融機関との交渉など、法的かつ実務的な対応に精通しています。また、手続きの各段階で必要な書類や対応の順序を明確にしてくれるため、無駄な時間や費用を抑えることにもつながります。
さらに、調停や審判に進展した場合でも、専門家が代理人として対応してくれることで、精神的な負担を大きく軽減できる点も見逃せません。相続は感情の絡む問題であると同時に、法律的な解釈や判断が必要とされる場面も多いため、第三者の冷静な視点は非常に貴重です。 結果として、専門家のサポートを得ることで、より円滑で納得のいく相続手続きが実現する可能性が高まります。時間や労力を節約し、最終的な結果に満足するためにも、早い段階で専門家に相談することが賢明な選択といえるでしょう。
相続手続きにおいて、相続人の一部が居所不明や連絡不能という状況は、手続きの大きな障害となります。居所が不明な場合には不在者財産管理人の選任が可能ですが、居所が分かっているにもかかわらず連絡が取れない場合は、さらに複雑な対応が求められます。
預金の解約については、金融機関の判断次第で念書提出などの方法により柔軟な対応が取られることもあります。金融機関も未処理の案件を減らしたいという事情があるため、リスクのない範囲で協力してくれる可能性はあります。 しかし、こうした一連の手続きは、法的な知識と実務経験が必要な場面も多く、個人で対応するには限界があります。だからこそ、相続に強い専門家を上手く活用することで、余計なトラブルや無駄な労力を避け、最終的に良い結果につなげることが可能になります。
○相続人の一人と連絡が取れない場合、相続手続きはどう進めればよいですか?
相続手続きは原則として相続人全員の同意が必要です。連絡が取れない相続人がいる場合、まずは所在調査や連絡の試みを行い、それでも不可能な場合には不在者財産管理人の選任申立てを検討します。居所が判明していても連絡がつかない場合は調停や審判に進むこともあります。
○居所不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任はすぐにできますか?
いいえ、不在者財産管理人の選任には裁判所への申し立てと調査資料が必要です。数週間から数ヶ月かかることもあり、申立書類や証拠資料を整えることが求められます。弁護士など専門家のサポートを受けるとスムースです。
○預金の相続については、相続人全員の同意がなくても解約できるのですか?
ケースによっては可能です。金融機関によっては、相続人の一部が連絡不能であっても、他の相続人による念書の提出や連絡履歴の提示によって解約に応じる場合があります。金融機関も未処理案件を減らしたい意向があるため、柔軟な対応をしてくれることがあります。
○不動産が含まれる相続では、連絡が取れない相続人がいても手続きできますか?
原則としてできません。不動産の名義変更(登記)には、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書が必要です。そのため、預金のように金融機関の裁量で対応できる余地はなく、法的な手続きが必須となります。
○専門家に依頼するメリットは何ですか?
専門家は法的手続きに精通しており、状況に応じた最適な対応を提案してくれます。調停や審判に至る前の段階でも、金融機関や裁判所とのやり取りを円滑に進めてくれるため、精神的負担や時間的ロスを減らすことができます。
CONTACT
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
平日10-17時
24時間365日受付
対応地域
全国対応(海外含む)