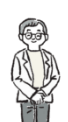相続対策とは?
相続対策とは、将来の相続に備えて財産の分配方法や税金対策を事前に考えておくことを指します。相続は突然発生することも多く、対策をしないままでいると、家族間のトラブルや予期せぬ税負担が発生する可能性があります。そのため、事前に準備を進めることが重要です。
まずは現状を正確に把握することが重要
相続対策の第一歩は、自分の財産を正確に把握することです。預貯金や不動産、株式などの資産だけでなく、住宅ローンやその他の借入金などの負債についても整理し、全体の財産状況を明確にする必要があります。財産の一覧を作成することで、「どの財産を誰にどのように残すか」を具体的に考えることができるようになります。
誰に、どの財産を、どのように残すかを考える
財産の全体像を把握したら、次に「誰に」「どの財産を」「どのように」残すかを考えます。例えば、不動産を特定の相続人に継がせたい場合は、遺言書の作成が有効です。一方、相続税の負担を軽減したい場合は、生前贈与や生命保険の活用等を検討することが必要です。このように、相続対策は単に財産を分けるだけでなく、受け取る側の状況や税金面も考慮しながら計画することが重要です。 相続対策は、現状の財産を把握し、誰に何をどのように渡すのかを整理することから始まります。その上で、自分に合った具体的な対策を選択していくことが大切です。
相続対策の主な方法
相続対策にはさまざまな方法がありますが、大きく分けると「財産整理」「相続税対策」「家族信託」「遺言」「任意後見契約」の5つが挙げられます。それぞれの方法を理解し、自分や家族の状況に合った対策を選ぶことが大切です。
財産の整理を行う
相続対策の第一歩は、財産を整理し、状況を明確にすることです。相続時に財産が不明瞭だと、相続人同士のトラブルにつながることがあります。そのため、生前に財産を整理し、どこに何があるのかを把握しておくことが重要です。
まず、財産目録を作成し、預貯金、不動産、有価証券、負債などをリストアップしましょう。財産の種類や価値を明確にすることで、適切な相続対策を検討しやすくなります。
また、不要な財産を整理することも大切です。例えば、使っていない不動産を売却したり、価値の低い資産を処分することで、相続人の負担を減らすことができます。特に、複数の相続人がいる場合、財産の分割が難しくなることがあるため、分けやすい形に整理しておくとよいでしょう。
相続税対策を行う
相続税は、財産の総額が一定額を超える場合に課される税金です。相続税の負担を軽減するためには、以下のような方法が有効です。
まず、生前贈与を活用することで、相続時の財産総額を減らすことができます。特に「暦年贈与制度」を利用すれば、毎年110万円まで非課税で贈与することが可能です。また、「相続時精算課税制度」を使えば、大きな額の贈与を行っても、一定条件のもとで相続時に税額を精算できます。
さらに、不動産を活用することも相続税対策の一つです。不動産は評価額が時価より低く算定されることが多いため、現金で保有するよりも税負担が軽減される可能性があります。加えて、生命保険を活用することで、非課税枠を活かしながら相続人に財産を残すことができます。
家族信託を活用する
家族信託は、財産の管理や承継をスムースに行うための仕組みです。特に、認知症対策として有効であり、判断能力が低下しても財産を適切に管理できるメリットがあります。
例えば、親が高齢になり、財産管理が難しくなった場合、家族信託を利用することで、子どもが代わりに管理・運用できます。これにより、相続発生前に財産が適切に管理され、不要なトラブルを防ぐことが可能になります。
遺言を作成する
遺言を作成することで、財産の分配方法を明確に定めることができます。特に、法定相続分と異なる配分を希望する場合や、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合に有効です。
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式不備による無効リスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため、法的に有効性が高く、安全性も確保されます。
任意後見契約を活用する
判断能力が低下した場合に備える制度として、任意後見契約があります。これは、認知症などで判断能力が失われる前に、信頼できる人を後見人として選び、財産管理や契約手続きを委任する制度です。
例えば、高齢の親が自宅を売却したい場合、本人の判断能力が不十分だと手続きが難しくなります。しかし、任意後見契約を結んでいれば、指定した後見人が代わりに手続きを進めることができます。これにより、相続発生前の財産管理をスムースに行うことが可能になります。
早めの対策がポイント
相続対策は、できるだけ早い段階で取り組むことが大切です。なぜなら、相続対策には「判断能力」が必要であり、年齢を重ねるにつれて、財産の管理や意思決定が難しくなる可能性があるからです。
判断能力が必要な理由
相続対策として行う「財産整理」「遺言の作成」「家族信託」「任意後見契約」などの手続きは、いずれも本人の判断能力があるうちに行う必要があります。特に、認知症を発症し、判断能力が著しく低下してしまうと、遺言を作成することができず、家族信託や任意後見契約も締結できなくなってしまいます。その結果、財産管理が困難になり、家族が望む形で相続を進められない可能性が高くなります。
家族の負担を減らすために早めの対策を
相続対策を先送りにすると、相続が発生した際に家族が大きな負担を抱えることになります。例えば、財産が整理されていない状態で相続が発生すると、相続人が財産を把握するだけでも時間がかかり、手続きが複雑になります。また、相続税対策をしていないと、予期せぬ高額な税負担が発生することもあります。
早めに準備を進めておけば、財産の分け方や税負担の軽減策を計画的に進めることができ、家族の負担を最小限に抑えることができます。
「まだ早い」と思わずに計画を始めよう
相続対策というと、「自分にはまだ早い」と考える方も多いかもしれません。しかし、相続はいつ発生するかわからないものです。また、相続税対策の一つである「生前贈与」は、長期間にわたって計画的に行うことで効果が高まります。そのため、「早すぎる」ということはなく、むしろ早めに対策を始めたほうが、余裕を持って準備を進めることができます。
相続対策は、健康で判断能力が十分にあるうちに始めることが最も重要です。早めに準備を進めることで、自分の意向に沿った形で財産を引き継ぐことができ、家族の負担を減らすことにつながります。
相続対策は当事務所にご相談ください
相続対策は個々の状況によって適切な方法が異なるため、専門家に相談することが重要です。相続税の負担を軽減する方法や財産の分配方法などは複雑であり、自己判断で進めると意図しないトラブルを招く可能性があります。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な対策を講じることができます。
当事務所は司法書士事務所ですが、相続対策全般について豊富な経験がございます。相続対策に精通した税理士と連携してお客様のニーズに合った相続対策をご提案いたします。
サービス内容・料金
| 個別にお見積りいたします |
- ご契約まで
- 〇事前のご相談(無料)・お見積り
〇相続対策に関する業務委託契約の締結
- サービス内容・流れ
- ①財産の整理・財産目録の作成
財産が分かる資料(預貯金通帳、不動産関係資料、証券関係資料、保険関係資料等)をお預りします(コピー可)。
②相続対策に関するレポートの作成
ご依頼内容に沿ったレポートを作成します。
④相続対策レポートの説明と具体的な対策の実行計画を立案
レポートの内容を詳しくご説明します。そして具体的な対策費用のお見積りを提示して何を行うか決定します。
⑤生前贈与、生命保険の加入、遺言作成、家族信託等の具体的な対策を実行
※ 相続対策サービスは税理士と連携して行います。税金に関わる業務は税理士が行います。