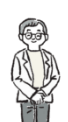暮れも押し詰まったある日、取引金融機関の担当者・山田さんから電話が入りました。
「藤川さん、年末のお忙しいときにすみません。ちょっと面倒な案件が起こりました。力を貸していただけませんか」
「面倒な案件ですか・・・・・・、着手は早いほうがいいんですよね」
「そうなんです。明日、相続人の奥様に会ってもらえませんか。資料はこれからすぐにメールします」
翌日、私は依頼人のご自宅へ伺うことになりました。待ち合わせは下町の雰囲気が残るJR総武線の平井駅。依頼人の自宅までの道すがら、山田さんは状況の説明をしてくれました。
「つまり、亡夫は前妻との間に子どもがいたことを奥様には話していなかったということですね」
「ええ。相続の手続きを当社で行うなかで、戸籍謄本を取り寄せたところ、この事実が判明したんです。奥様は気が動転してしまって。これから伺うご自宅も、奥様の妹さんの持ち家で、長年、ご夫婦で住まわせてもらっていたようなんです。だから遺産といっても、不動産はなくて、預貯金だけです。奥様としては、これから妹さんとその預貯金で生活していこうと考えていたようなんです」
「奥様はびっくりされたでしょうね。まずはお話をお伺いして、お気持ちを確認しましょう」
相続人である須藤洋子さんのお住まいは、路地裏の道幅2メートルほどの道路の両側に小さな木造2階建ての家が立ち並ぶなかの一軒でした。
夫・健一さん(享年88歳)亡き今、83歳の洋子さんと、洋子さんの妹・大垣明子さん(78歳)の二人暮らしです。つましく生活している様子で、仏壇はなく、背の低い箪笥の上に遺影と位牌が置かれているだけでした。
「何しろ狭い家なので、仏壇も買ってあげられなくて。それに私たち姉妹もいつまで元気でいられるかわかりませんからね」
と、ご遺影に手を合わせる私に、まるで言い訳をするかのように話しました。
「今回は本当にびっくりなされたでしょう? 今日は、洋子さんがこれからどうなされたいか、お気持ちをお伺いに参りました」と私が話し始めると、堰を切ったように、洋子さんは納得できない気持ちを訴えかけてきました。
「夫に離婚歴があることは知っていました。けれど子どもがいたなんて、そんなこと30年も一緒に生活してきて、一言も言わなかったんです。ひどいと思いませんか。戸籍謄本をとったら、いきなり子どもがいたんですよ。夫が残してくれた預貯金2000万円を半分にしなければならないなんて。もちろん夫が稼いだお金を貯めたものですが、私だって妻として夫を助けてきたんです。そもそも妹の家に住まわせてもらったから、貯金ができたんですよ。そうじゃないですか。それなのに、法律ではこの子に半分の権利があるなんて。それは納得できません」
洋子さんは、このお金で妹さんにもこれまでのお礼ができると考えていたようで、そうした予定もこの子の出現で全部崩れてしまったことが、どうにも納得いかないようでした。
「法律上は確かにこのお子さんに半分の権利がありますから、まずはお子さんに私から連絡を取ってみますが、よろしいでしょうか」
「どうかよろしくお願いします」と洋子さんは私の手を握って頭をさげられました。
私はまずは、この長男に手紙を書いてみることにしました。