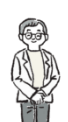遺産相続は相続人の考え方次第
子供のいない夫婦で、配偶者と他方の兄弟姉妹が共同相続人となる場合の配偶者の法定相続分は4分の3と誰よりも多く定められています。したがって、このケースでも法律に則れば、明子さんは5000万円の4分の3の3750万円を相続できます。けれども5000万円相続できると考えていた明子さんは、これでは納得できなかったのでしょう。
もし明子さんが希望するように、二郎さんの遺産を2500万円とすれば、明子さんは4375万円を相続することになります。これが、明子さんが譲れるぎりぎりの金額のようです。
相続人は二郎さんの一番上のお姉さん、お兄さん、ニ番目の亡姉さんの子ども二人、亡弟、亡妹にそれぞれ子どもが一人ずつです。明子さんの希望通りに遺産分割した場合、この6人で残りの625万円を分けることになります。
早速私は、明子さんの希望を記した手紙を添えて、財産目録とそれぞれの法定相続分を記載した書類に、皆さんの意向を確認したいという内容の手紙をつけて、6人の相続人に送りました。
同封した明子さんの手紙は短いながらも心のこもった内容で、預金は共働きでつましく生活しながら二人で築いた財産であること、これから一人で生活するために夫婦で築いたこの財産を使って施設に入るつもりでいたこと、幾ばくかのお金はお渡しするが、一人で生きていくことに不安があるので、少しでも手元に財産を残したいことなどを切々と書かれていました。
手紙を出したところ、すぐに相続人たちから連絡が入りました。
亡妹のお子さんからは「相続しない」と言っていただき、ハンコ代として3万円の商品券をお送りしました。
お兄さんと亡次姉のお子さん(二人)、亡弟のお子さんからは、明子さんの希望通り預金の半分を基準に法定相続分を相続したいという返事がきました。そこで、それぞれに125万円ずつ、合計375万円を振り込むことで、了承いただきました。
ところが、九州に住む長姉は明子さんの希望を一切受け付けず、「法定相続分をきっちり相続する」という手紙が送られてきました。
明子さんはもちろん納得いきません。そこで、もう一度、明子さんはこの義姉に手紙を書くことにしたのです。
二回目の手紙には、なぜ預金の半分が明子さんに権利があると考えるのかについて、さらに詳しく記されていました。――都営住宅で質素に生活していたこと、生活費は明子さんが全額出していたこと、子どもを授からなかった経緯、そのための不安などについても正直な気持ちが切々と書かれていたのです。
その手紙を出してすぐ、長姉の息子のお嫁さんから私に電話が入りました。長姉は90歳を超える高齢で、自分ではやり取りができないため、この女性が窓口になっていました。
「義母は、絶対に法定相続分をもらうと言っています。これ以上お手紙をいただいても義母の考えは変わらないと思います。250万円いただきます」
この女性の事務的な対応に、正直私はびっくりしました。
そこで明子さんが長姉さんと直接電話でお話しできないかと、何度かお願いしたのですが、「義母は耳も遠いですし、無理です」とけんもほろろに返されたのでした。
明子さんは長姉の対応に最後まで納得されなかったのですが、これ以上の話し合いは無理であること、どうしても納得いかないなら弁護士を入れて裁判になることをご説明し、渋々ではありましたが了承していただきました。
民法上、配偶者の権利は優遇されており、このケースでも遺産である預金の4分の3は配偶者である明子さんの権利となります。しかし、今回のように遺産の形成過程に特別な事情があるケースでは、形式的に預金全額を夫の相続財産として協議を進めるのはバランスを欠いてしまうと、私は考えています。
実際、このケースでも遺産形成の背景や夫婦の事情を考慮して、相続を希望しない、あるいは法定相続分よりも少ない相続で了承していただけた相続人はいました。
遺された配偶者の想いや意向をきちんと伺い、それを他の相続人に伝えることで、協議結果が変わる可能性があるのだとすれば、私はそのお手伝いをしたいと考えています。それが相続業務にかかわるうえでの私のやりがいにもなっています。
しかしながら、こういうケースを担当すると、遺言書の作成の必要性を強く感ぜずにはいられません。生前から司法書士が相続に関わっていくことの大切さを実感した案件でした。
終わり