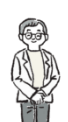遺産を相続人一人に集めて、贈与する
戸籍の附票を取り寄せた結果、勇一さんの母と前夫の間には子どもが二人(男女)いましたが、二人とも既に亡くなっていることがわかりました。その亡兄には子どもが三人、亡姉には子どもが一人おり、それぞれ附票から住所が明らかになりました。
次に、勇一さんの希望通り、和子さんの財産を孝さんが受け取る方法の検討に入りました。やはり相続人全員から孝さんへ贈与してもらうしか方法はないのですが、八人それぞれから贈与してもらうとなると、手続きが煩雑になるだけでなく贈与税もそれぞれに発生し、孝さんにとっても面倒になります。
そこで、勇一さんを除く相続人全員の相続分を勇一さんに譲渡してもらい、勇一さんから孝さんに贈与するという方法と取るのが一番スムースに相続手続きを進められると考え、勇一さんに提案することにしたのです。
「なるべく早く孝さんにお金が渡せるなら、私に異論はありません。手続きを進めてください」と勇一さんの了解を得て、私はさっそく母方の相続人(勇一さんの甥姪たち)と連絡を取るべく動き出しました。
その際、勇一さんに「相続に関するお願い」という文書を書いていただきました。内容は、和子さんの遺産の大半を内縁の夫である孝さんに渡すために、まずは自分に相続分を譲渡していただきたいというものです。和子さん名義の預金ではあるものの、二人で形成した財産であり、私たち相続人はこの財産形成には関与していないこと、年金の不足分を預金を取り崩して生活していた孝さんは、お金を下ろすことができず困窮している現状などが記されていました。
こうして私は、勇一さんのお願い文書と譲渡の意向を伺う文書を同封し、相続が発生した旨を知らせる書類を母方の相続人に送付しました。
ほどなくして母方の相続人四人を代表して亡兄の息子から、すべての相続財産を勇一さんに譲渡するという連絡がありました。これで母方の相続人四人の勇一さんへの譲渡が決まりました。
その後、すでに勇一さんから譲渡すると伺っている妹・京子さん、父方の亡姉の子ども二人から正式に遺産譲渡意向の文書を提出していただき、やっと相続手続きに入ることができたのです。
贈与税負担を考えて、1年間300万円ずつ贈与することに
勇一さんから相談を受けてから約1カ月後、すべての手続きが完了し、和子さんの預金はすべて勇一さんの名義となりました。
さてこれからはこのお金をどのように孝さんに渡していくかを考えなければなりません。
当然、他人からの贈与になるわけですから、贈与税が課せられます。そのことをまず孝さんには理解していただく必要があります。私は、勇一さんにも同席していただき、孝さんと面談をしてお金の渡し方を説明することにしました。
勇一さんをはじめとする相続人全員の計らいで、和子さんのお金が自分のお金になることが決まり、孝さんは本当にうれしそうでした。
ただ、贈与税がかかるという話をはじめたとたん、「私が稼いで貯めた金なのに……」と顔を曇らせました。
そこで私は、年間110万円までの贈与なら非課税であること、200万円までの贈与なら税率が10%に抑えられること、もし和子さんの預金全額をいっぺんに贈与したら税率が45%かかることを一つずつ説明し、次のような提案をしました。
「贈与税を支払うことは避けられませんが、少なくすることはできます。300万円の贈与なら贈与税は19万円ですみます。2000万円の贈与なら贈与税は600万円以上になります。毎回19万円の贈与税は発生しますが、毎年300万円ずつ、山本様から贈与される形を取られたらいかがでしょうか」
この方法なら5~6年程度で財産の移転を終わらせることができるうえ、節税もできます。
孝さんは税金を取られることに納得していませんでしたが、この方法ならかなりの節税になることはご理解いただけたようで、この方法で財産移転をしていくことで、勇一さんと孝さんの間で贈与契約書を作成したのです。
すべての手続きが完了したことを報告するため勇一さんに電話したところ、「本当にいろいろありがとうございました。この贈与契約は、たとえ私が孝さんより先に亡くなったとしても続けるように、子どもたちには話しておきました。そうすればあの世で和子に文句を言われなくてすみますからね」と話されました。
事実婚の夫婦間では、遺言書がない限り相続は不可能です。人生100年時代、中高年になってからの結婚は面倒だからと、籍を入れずにパートナーとともに生きる人生を選ぶ方も増えてくるでしょう。
今回は相続人らの計らいで内縁の夫に財産を渡すことができましたが、一人でも反対すればうまくいかなかった案件でした。残されたパートナーが路頭に迷わないよう、やはり遺言書の作成はこれからますます大切になってくると思います。
終わり